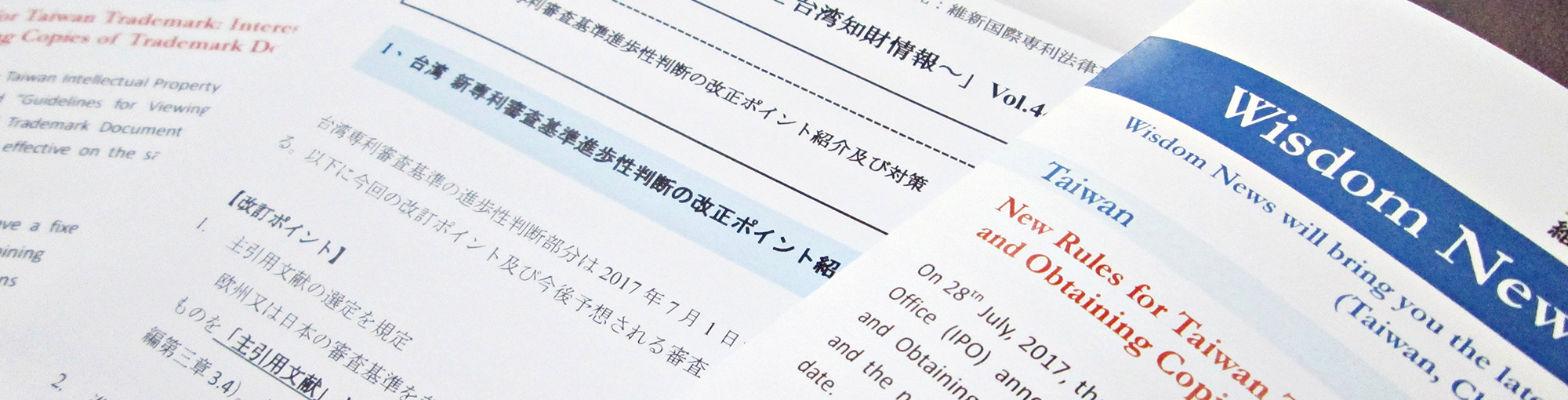「〇〇市集」は商標登録できるのか?-台湾における使用による識別力の獲得及び使用証拠の認定基準の紹介
Vol.144(2024年8月23日)
事件の事実
ECサイト「科研市集」は、台湾企業「勢得科研股份有限公司(英語名:STAREK SCIENTIFIC CO., LTD.、以下、勢得社という。)」が提供する台湾初の科学研究用品や実験室での消耗品を専門に販売するプラットフォームである。勢得社は2018年12月6日に台湾特許庁へ「科研市集」商標の出願を行い、翌年12月16日に使用による識別力が獲得されたことを理由に第02031242号商標(以下、本件商標という。)として登録された。
しかし、「科研市集」を企業名とする「科研市集有限公司(以下、科研社という。)」が本件商標に対して異議を申立て、本件商標の「科研市集」は「科学研究用品の売買を行う場所」という意味であり、固有の識別力を有するものではない上、本件商標の出願時から僅か1年間しか使用しておらず、使用による識別力を獲得したとは言い難い、と主張した。本件の審理の後、台湾特許庁は、勢得社が本件商標を使用したのは2年程度であるが、使用証拠が示すように、販売量及び市場シェアは非常に大きく、ソーシャルメディアの統計データも参酌すると、本件商標は関連消費者の購買決定に対して一定の影響力があることが分かるとの見解を示し、本件商標登録を維持する旨の決定を下した。科研社はこれを不服として、経済部訴願審議会に訴願を提起した。
| 商標 | 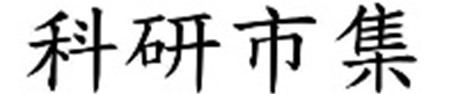 |
| 商標権者 | 勢得科研股份有限公司 |
| 出願日 | 2018年12月6日 |
| 登録日 | 2019年12月16日 |
| 指定商品・役務 | 第1類 工業用化学品、科学用化学品、化学試薬。 第9類 実験室用機器、ビーカー、化学装置、化学機器…等。 第35類 金物の小売又は卸売、化学製品の小売又は卸売、代理輸出入サービス…等。 第42類 研究及び開発の提供、他人のための新製品の研究及び開発…等。 |
その後、勢得社は知的財産及び商事裁判所(以下、知財裁判所という。)に行政訴訟を提起したが、知財裁判所により訴願審議会が採用した見解を支持する旨の判決が下され、2022年4月に110(2021)年度行商訴字第78号行政判決で敗訴判決が下された。勢得社はさらに最高行政裁判所に上訴したが、最高行政裁判所は2024年2月に最高行政法院111(2022)年度上字第463号判決で当該上訴を棄却し、原審を支持する旨の判決を下した。
知財裁判所(一審)の見解
- 本件商標が固有の識別力を有しないと認定したことについて
(1) 本件商標は、デザインされていない横書きの漢字の「科研市集」から構成されている。また、「科研」という言葉は、辞書に収録されていないが、台湾におけるその他法律の規定では、「科研採購(日本語訳:科研買付)」という言葉は「科学技術研究発展採購」の略称であり、「科研」は科学技術研究又は科学研究を意味することが分かる。この他、辞書によれば、「市集(日本語訳:マルシェ)」は商品を販売する場所を意味しており、また台湾特許庁が公告した『権利不要求の声明が不必要な事例』として収録されている識別力を有しない文字に該当する。
(2) 勢得社は、他の「市集」という言葉を含む第三者の登録商標を示したが、それら商標には識別力を有するその他の文字又は図形が含まれており、本件とは状況が異なる。前にも述べたように、本件の「科研市集」商標が消費者に与える印象は「科学研究に関連する商品又は役務」であり、固有の識別力を有していない。
- 本件商標が使用による識別力を獲得していないことについて
(1) 本件の事実状態を判断する基準時は、本件商標出願の登録査定時とするべきである。
(2) 勢得社が提出した証拠資料によれば、大多数が本件商標登録日以降の使用証拠であるため、使用により識別力を獲得した証拠資料とすることはできない。
(3) たとえ本件商標登録日前における本件商標の実際の使用証拠が、ビーカーの図「 」と組み合わせたものであったり、英文字の「sciket」と組み合わせたものであったり、又はこの2つを組み合わせた「
」と組み合わせたものであったり、英文字の「sciket」と組み合わせたものであったり、又はこの2つを組み合わせた「 」であったとしても、いずれも本件商標を単独で使用した証拠ではないため、本件商標が使用により識別力を獲得したことを証明することは困難である。
」であったとしても、いずれも本件商標を単独で使用した証拠ではないため、本件商標が使用により識別力を獲得したことを証明することは困難である。
以上をまとめると、知財裁判所は本件商標が商標法第29条第1項第1号に規定されている商標登録を受けることができない場合に該当し、且つ原告が提出した証拠では、本件商標が使用による識別力を獲得したことを証明できないと認定したため、原告に敗訴判決を下した。
最高行政裁判所(二審)の見解
最高行政裁判所は概ね知財裁判所の見解を支持しており、さらに以下の説明を付け加えている。
(1) 標識が使用による識別力を獲得しているか否かの判断は、商標権者が提出した証拠資料について、当該標識が使用されることにより台湾の消費者が当該標識と商品又は役務の出所を関連付け、出所の識別ができる標識になっているかを総合的に審理しなければならない。
(2) 勢得社が提出した証拠には、電子メールの署名欄、関連消費者の検討資料、業者との提携契約書、公共バスにおける広告、各種イベント及び受賞資料が含まれていた。しかし、いずれもその他の要素と結合していたものであっため、消費者が本件商標のみから、当該商標が特定の出所を示すものであると認識できたことを証明できない。
(3) この他、商標が使用による識別力を獲得しているか否かについては、当該商標の指定商品又は役務における実際の使用証拠により認定すべきである。上記の契約書及び検討資料などの使用証拠はいずれも、第35類の化学製品の小売及び卸売などのサービスにおける使用を証明するものに過ぎず、勢得社の「第35類の化学原料用品を購入する消費者は、将来的に工業化学品、実験室機器、金物、代理輸出入サービスを購買又は使用する可能性があるため、当該消費者群は同様に第1、9、42類及び第35類のその他の指定商品・役務における消費者でもある」という主張には理由がなく、採用することができない。
以上の理由から、最高行政裁判所は上訴を棄却した。
- 使用証拠はできる限り、関連商標のみが使用されたものを選択する
宣伝広告のため、企業は商標をその他の要素と結合させること、例えば、図形や色彩デザイン等を追加したりすることがよくある。もしこのような宣伝資料を使用証拠とする場合、「商標自体が識別力を有する」のか、「図形を追加した商標が識別力を有する」のか疑問が残る。
本件判決において、最高行政裁判所は、勢得社により提出された証拠資料において商標がいずれもその他の要素と結合されたものであったため、消費者が本件商標のみから、当該商標が特定の出所を示すものであると認識できたことを証明できない、と指摘している。
実際に使用する際には、必ずといっていいほど商標にその他の図形、色彩、デザインされた文字と組合わせて使用される。そのため、初めからその他の要素と組み合わせた商標を出願しておくことが考えられる。
- 国外における使用証拠も提出できることを念頭に入れておく
『識別力審査基準』の第5点において、使用による識別力の獲得について、台湾国内の関連消費者の認知を判断基準としなければならないと規定されている。しかし、国外における使用資料を提出し、併せて国内の関連消費者もそれらの国外における使用状況を把握していることを証明できれば、国外における使用資料であっても使用証拠として認められる。