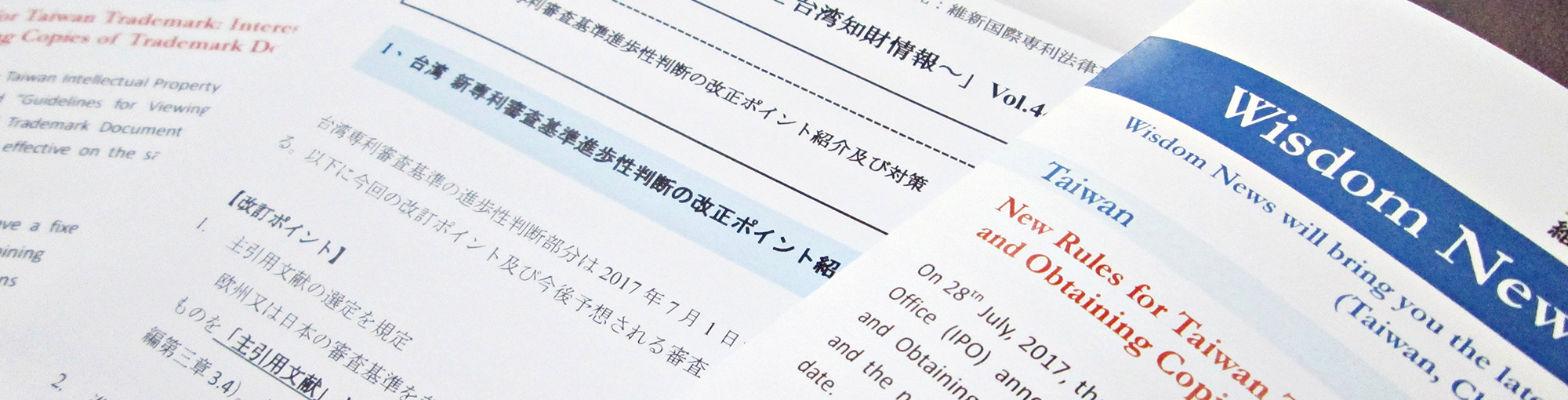台湾 特許請求項中の素子及びその配置関係の用語解釈の原則を改めて強調した判例(発光デバイス事件)
Vol.149(2025年4月11日)
事件経緯
億光電子工業股份有限公司(原告)は、台湾特許第I553264B号、第I644055B号、第I665406B号(以下、本件特許1~3と称し、合わせて「本件特許」と称す)の特許権者であり、LED産業の重要企業である。
原告は展晟公司(被告)がOEM依頼し、輸入及び販売しているA類本件製品(電極の構造が凹形)及びB類本件製品(電極の構造が凸形)が本件特許請求項の文言侵害に該当すると考え、「允晟、立晟、展晟三社が共同で『展晟グループ』の名義で本件製品を販売しているため、連帯賠償責任を負うべきである」と主張し、知的財産及び商事裁判所に訴訟を提起した。
被告は、原告から提出された製品写真では被告らの権利侵害行為を証明するに足りないと主張する共に、乙証22~31により本件特許1~3が新規性及び進歩性を有しないことを証明できると特許無効の抗弁を主張した。
裁判所は、本件特許1~3は新規性及び進歩性を有しないと認定し、原告敗訴という判決を下したが、本件判決における主な論旨は、特許請求の範囲解釈に関する認定である。
本件特許の技術内容
本件特許は、発光ダイオードチップを収めるためのリードフレーム、及び、前記リードフレームから作られる発光デバイスに関する。
本件特許1請求項1において、以下の内容が記載されている。
「それぞれが電極部断面を有する少なくとも1つの電極部と、
筐体断面を有し、前記少なくとも1つの電極部の少なくとも一部を覆う筐体と
を含み、
前記筐体断面又は前記電極部断面は、少なくとも1つの湾曲面を含むことができる、
キャリア。」
【図2.1.1キャリアリードフレームの実施態様の一部模式図】
【図2.1.2実施例における発光デバイスの平面図】
本件特許2請求項1において、以下の内容が記載されている。
「電極部断面を有する少なくとも1つの電極部と、筐体断面を有する筐体とを含む、キャリアと、
前記キャリアに固定される、発光ダイオードチップと、
を含み、
前記筐体断面と前記電極部断面は、同レベルにない、
発光デバイス。」
【図2.2.2実施例における発光デバイスの平面図】
【図2.2.3異なる実施例における発光デバイスの平面図】
本件特許3請求項1において、以下の内容が記載されている。
「ウィング部分を含む少なくとも1つの電極部と、前記少なくとも1つの電極部の一部を覆う筐体とを含む、キャリアと、
前記キャリアに固定される、発光ダイオードチップと、
を含み、
前記ウィング部分は、前記筐体の外側に露出され、かつ中央領域と少なくとも1つのエッジ領域とを含み、
前記少なくとも1つのエッジ領域は、前記中央領域から突出し、
前記少なくとも1つの電極部は、電極部断面を含み、
前記筐体は、少なくとも1つの筐体断面を含む、
発光デバイス。」
【図2.3.2実施例における発光デバイスの平面図】
本件の主な争点は、本件特許請求項の「電極部断面」、「筐体断面」、「同レベルにない」、「突出」という用語に対する解釈方法である。
知的財産及び商事裁判所の見解
一、 請求項に対する解釈は、特許請求の範囲を基準に、明細書及び図面を参酌しつつ、内部証拠の適用を優先すべきである
特許請求の範囲を解釈する際に、発明の説明及び図面は補助的な立場にあるが、請求項において、保護しようとする範囲に関する必要な記述しか記載されていない、又は明確でない部分があることが多い。この場合、発明の目的、技術内容、特徴、及び効果を理解するために、明細書及び図面を参照する必要がある。これにより、請求項の実質的な内容を特定することができる。
特許請求の範囲解釈では、内部証拠(請求項の文言、発明の説明、図面、及び包袋)と外部証拠(当業者の見解、教科書等の内部証拠以外のその他の証拠)を参酌することができるが、内部証拠の適用を優先すべきである(最高行政裁判所2014(103)年度判字第417号判決の要旨を参照)。
二、 本件特許請求項の「筐体断面」、「電極部断面」に対する解釈について
原告の主張は、以下の通りである。
「筐体断面」は切断面を指し、例えば、加工プロセスにおいて残留物を除去した後にキャリアの筐体上に形成されるものである。同じように、「電極部断面」も切断面を指し、例えば、加工プロセスにおいて延伸部を除去した後にキャリアの電極部上に形成されるものである。
一方、被告らの抗弁は、以下の通りである。
「電極部断面」は「延伸部を除去した後に電極部の表面に形成されるものに限らない」と解釈すべきであり、「筐体断面」は「残留物を除去した後に筐体の表面に形成されるものに限らない」と解釈すべきである。
分析した結果、「筐体断面」、「電極部断面」等の用語は、請求項の文字のみによる解釈からは明確にならない。本件特許明細書【0022】において、「除去段階の後、少なくとも1つの電極部断面が、延伸部によって、キャリアの電極部上に形成され、除去段階の後、筐体断面が、残留物によって、キャリアの筐体上に形成される」と記載されているほか、【0047】と図14、15、及び【0048】と図16において関連の記載があるが、それ以外の説明がないため、本件特許の包袋を参酌すべきである。
本件特許の出願段階で原告から提出された意見書において、以下の内容が記載されている。
「具体的に、請求項1の電極部断面及び筐体断面とは、切断面を指し、例えば、加工プロセスにおいて延伸部を除去することで定義される技術的特徴(明細書【0022】を参照)であり、更に、これらの断面は湾曲面を有すると定義できる。」
このことから、本件特許1の出願段階において、先行技術と区別して進歩性を有することを示すために、原告は既にこれらの用語の設置形態に対する解釈を限定していたことは明白である。よって、請求項の文言上の意味に基づき、明細書、図面及び包袋内容を参酌して解釈を限定することで、本件発明が解決しようとする課題・技術手段・効果の三者から構築される発明の思想を反映することができる。
したがって、「筐体断面」は「残留物を除去した後にキャリアの筐体上に形成される切断面」と解釈すべきであり、「電極部断面」は「延伸部を除去した後にキャリアの電極部上に形成される切断面」と解釈すべきである。
被告らは、「これらの材料に対して連続的に行われる除去工程のいずれにおいても『切断面』が形成される」と抗弁しているが、本件特許明細書【0022】において、「筐体断面」と「電極部断面」の限定条件が明確に記載されているため、被告らが主張している「筐体断面」と「電極部断面」に対する解釈は、被告らの主観的な見解であり、外部証拠に該当する。
証拠を参酌して「筐体断面」と「電極部断面」を解釈する際には、本件特許明細書を優先すべきであり、仮に被告らが主張している限定なしという条件で「筐体断面」と「電極部断面」を解釈すると、本件発明が解決しようとする課題及び技術手段に反することとなるため、被告らの主張は採用できない。
三、 本件特許請求項の「同レベルにない」に対する解釈について
原告の主張は、以下の通りである。
「同レベルにない」とは、筐体断面と電極部(ウィング部分)が接続している状況において、電極部断面と筐体断面がキャリアの同じ面にあるが、平面を形成しないことを指す。
一方、被告らの抗弁は、以下の通りである。
「前記筐体断面と前記電極部断面は、同レベルにない」という特徴は、「前記筐体断面と前記電極部断面が接続しているか否か、又は、キャリアの同じ面にあるか否かにかかわらず、前記筐体断面と前記電極部断面は平面を形成せず、かつ前記筐体断面と前記電極部断面は残留物と延伸部とを同時に除去することにより形成されるものではない」と解釈すべきである。
分析した結果、本件特許明細書【0022】において、「更に言及すると、電極部断面及び筐体断面がキャリアの同じ面にある場合、電極部断面及び筐体断面は互いに同レベルにあってもよく(平面を形成する)、又は、互いに同レベルになくてもよい(平面を形成しない)」と記載されており、本件特許明細書【0023】、図1、5、及び本件特許明細書【0042】、【0051】と図12D、17Dの実施例においても、「前記筐体断面及び前記電極部断面は平面を形成しない(即ち、前記筐体断面及び前記電極部断面は同レベルにない)もの」と記載されている。
請求項の「同レベル」、「同レベルにない」という用語を、上記本件特許明細書及び図面の内容を参酌して解釈すると、「同レベル」とは、電極部断面と筐体断面がキャリアの同じ面にある場合に、前記電極部断面と前記筐体断面が平面を形成することができることを指し、「同レベルにない」とは、電極部断面と筐体断面がキャリアの同じ面にある場合に、前記筐体断面と前記電極部断面が平面を形成しないことを指す。
被告らは、発明が解決しようとする課題及び技術手段を満たすために、「かつ前記筐体断面と前記電極部断面は残留物と延伸部とを同時に除去することにより形成されるものではない」という解釈を追加すべきであると主張している。
しかし、このような解釈は本件特許明細書又は図面で開示されているが請求項に記載されていない内容を請求項に読み込むものであり、被告らの上記主張が「読み込み禁止の原則」に違反していることは明らかである。
原告は、本件特許明細書【0022】、【0023】、【0042】の内容から、「同レベル」、「同レベルにない」とは筐体断面と電極部(ウィング部分)が「接続している」必要があることを指すと主張している。
しかし、分析した結果、本件特許明細書【0022】の記載によれば、同レベル又は同レベルにないことを判断する根拠は、主に筐体断面と電極部断面が平面を形成するか否かであり、筐体断面と電極部(ウィング部分)が「接続している」必要はない。請求項の文言を過度に解釈すると、読み込み禁止の原則に違反する可能性があるため、原告の主張には理由がない。
四、 本件特許請求項の「突出」に対する解釈について
被告らの抗弁は、以下の通りである。
本件特許各請求項に記載されている「中央領域」、「エッジ領域」、「筐体断面」という用語は、その位置が限定されていないため、請求項に記載されている「から突出する」という用語が構造を不明確なものにしている。また、本件特許の目的及び手段を満たすために、「前記筐体断面と前記電極部断面は残留物と延伸部とを同時に除去することにより形成されるものではない」という解釈を追加すべきである。
しかし、被告らの主張は、請求項において明確な解釈が示されている「中央領域」、「エッジ領域」、「筐体断面」等の文言を明細書の内容から更に読み込むものであり、本件特許請求項に対する不合理な限定であるため、読み込み禁止の原則に違反している。
五、 本件特許の新規性及び進歩性について
原告の主張は、以下の通りである。
本件特許1 のN03号特許無効審判において、請求人から提出された乙証26の開示内容から、乙証26に係る発明が残留物を除去した後にキャリアの筐体上に形成される切断面である「筐体断面」を有するか否かを直接かつ一義的に知ることができない。
分析した結果、乙証26の材料固定部34は、プラスチック材料を切除した後に表面実装型溶接突起部 27の両側に筐体断面を形成する。また、乙証26、27に係る発明は、いずれも材料固定部によるプラスチック材料のモールド技術、及びプラスチック本体とチップ固定部と溶接突起部を象嵌成形で一体化したLEDパッケージ技術を使用するものである。
乙証26図9のプラスチック材料が材料固定部34に入り、象嵌成形した後に材料固定部34のプラスチック材料を除去すると、図3、4のプラスチック材料断面を自然に形成するため、原告の「直接かつ一義的に知ることができない」という主張は採用できない。
[1] 2023(112)年度民専訴字第18号判決