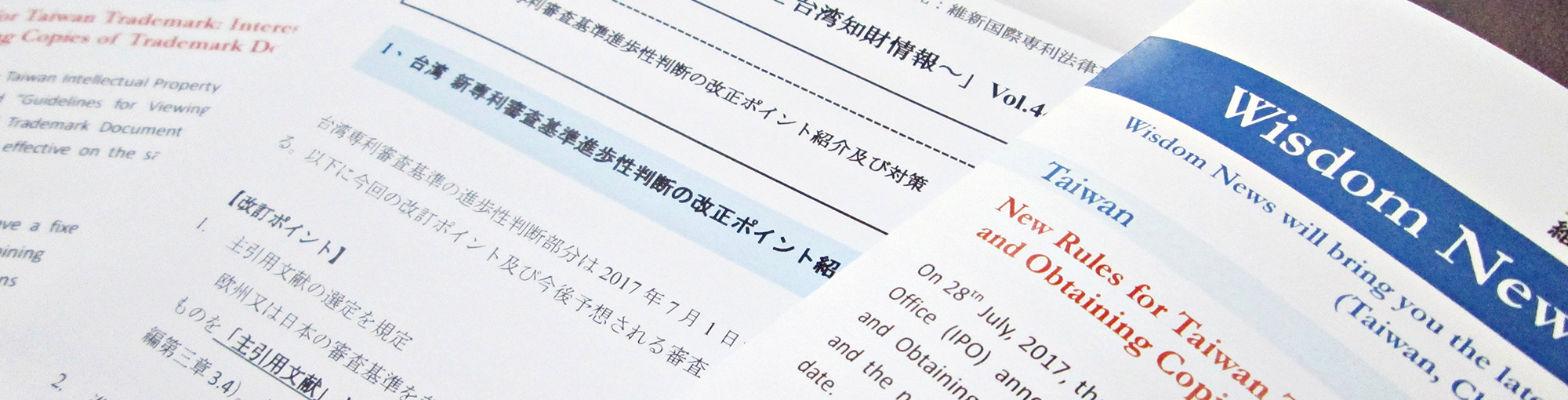台湾 バイオテクノロジー関連発明の進歩性判断に関する判例(3Dバイオプリンティング用バイオインクセット及びその応用事件)
Vol.148(2025年2月26日)
事件経緯
本件ではまず、台湾大学(原告)が2018年1月に出願した台湾特許出願第107102761号「3Dバイオプリンティング用バイオインクセット及びその応用(以下、本願発明)」は、審査の結果、拒絶査定が下された。原告は当該査定を不服として再審査請求を行い、その後請求項を補正したが、依然として進歩性を有しないと認定され、拒絶査定が下された。原告は当該査定を不服として訴願を提出したが経済部より棄却されたため、原告は本件行政訴訟を提起した。
裁判所は引用文献1~4で開示された内容に基づき、本願請求項1~13に係る発明は進歩性を有しないと認定し、原告敗訴の判決1を下した。
本願発明の技術的特徴
本願請求項1は初審査及び再審査において、下記の補正が行われた。
「バイオインクと、二価金属イオン溶液とを含み、
前記バイオインクは、生分解性ポリウレタン及び生体高分子を含み、
前記生体高分子は、ゼラチン、アガロース、アルギン酸塩、ヒアルロン酸及びその塩、キトサン、又はこれらの任意の組み合わせからなる群から選択され、
前記生分解性ポリウレタンと前記生体高分子との重量比範囲は85:15~5:95である、
細胞を担持可能な構造体のプリンティングに用いられるバイオインクセット。」
引用文献における開示状況
本願請求項1及び引用文献の技術的特徴を比較しまとめると、下記のようになる。
|
|
本願請求項1 |
引用文献12 |
引用文献23 |
|
技術的特徴1 |
バイオインクと、二価金属イオン溶液とを含み、 |
バイオインクは塩化カルシウム溶液と共に用いることができ、塩化カルシウム溶液により二次化学硬化反応を起こし、架橋重合を促進させる (第3129頁左枠第4段目、第3130頁左枠第2段目、第3130頁右枠第1段目) |
バイオインクと塩化カルシウム(CaCl2)とを併用した後、注射針(needles)で印刷することにより好適なゲル化を生じさせる |
|
技術的特徴2 |
前記バイオインクは、生分解性ポリウレタン及び生体高分子を含み、 前記生体高分子は、ゼラチン、アガロース、キトサン、又はこれらの任意の組み合わせからなる群から選択され、 |
バイオインクの処方として、①生分解性水分散系ポリウレタン(PU)、②動物由来の天然材料、例えばゼラチン等(第3122頁右枠末段)、③細胞、アルギン酸塩、カルボキシメチルキトサン等(第3129頁左枠第4段目)を含んでいてよい |
メタクリル酸メチルで修飾されたゼラチン (GelMA)、アルギン酸塩、光重合開始剤及び細胞からなるバイオインク |
|
技術的特徴3 |
前記生分解性ポリウレタンと前記生体高分子との重量比範囲は85:15~5:95である、 |
未開示 |
未開示 |
|
技術的特徴4 |
細胞を担持可能な構造体のプリンティングに用いられるバイオインクセット。 |
技術的特徴1と同様 |
技術的特徴1と同様 |
以上から、本願発明と引用文献に係る発明(以下、引用発明)との主な相違点は生体高分子の成分が若干異なる点、及び引用文献ではその含有量の比が開示されていない点であることが分かる。
知的財産及び商事裁判所の見解
知的財産及び商事裁判所は引用文献1、2の組み合わせにより、本願補正後請求項1の進歩性を否定できるとの見解を示している。その理由を以下に説明する。
1. 引用文献1において、バイオインクの処方はゼラチン、細胞、アルギン酸塩、カルボキシメチルキトサン等を含むことができることが開示されており、即ちこれらは本願発明に係るゼラチン、キトサン及びアガロースに相当する。そしてその効果を向上させるためにバイオインクにおける天然材料の成分組成及びその含有量比率を調整することは、当業者にとっての慣用技術である。
2. 原告は、本願発明に用いられる生体高分子は引用発明と異なるものであり、実験を通じてしかその特定の種類を知ることができないと主張しており、請求項を補正する際に、引用文献と重複する成分(例えばヒアルロン酸、アルギン酸塩等)を削除している。しかし引用文献1で開示されたバイオインクにおいて、その特定の組み合わせに係る成分(例えばゼラチン等)が具体的に例示されている。また本願請求項1が「前記バイオインクは、生分解性ポリウレタン及び生体高分子を『含み』」と開放式の形で記載されているため、バイオインクはこれら2種の成分の他にその他成分を含むことができる。よって、引用文献1で開示されたバイオインクがヒアルロン酸やアルギン酸塩等の成分を含むために、当該バイオインクが必ず本願発明と異なるものであるとは判断しきれない。
3. 原告は、引用文献1で開示されているキトサンはカルボキシメチル化されたものであり、引用文献2で開示されているゼラチンはメタクリル酸メチルで修飾されたものであるため、いずれも本願発明と異なる上、その効果やメカニズム等も異なると主張している。しかし本願請求項では「キトサン」、「ゼラチン」等の化合物に関する記載について特段の条件を設けていないため、当該請求項を解釈する際に下位概念に属する特定の化合物を除外すべきではない。したがって、置換基により置換されているものも、置換されていないものもいずれもこれら化合物の定義を満たすものであると認定すべきである。
また、引用文献1で「ゼラチン成分を含むバイオインクは、カルシウムイオンと反応させる(ゲル化する)架橋メカニズムを採用できる」と具体的に開示されており、これは本願発明で用いられている方法と実質的に同一である。
4. また原告は、本願発明では二価金属イオンと一定時間反応させると、引用発明より優れた24時間以上の構造安定化効果が得られると主張しているが、引用文献1において本願発明に係る特定の組み合わせが開示されているため、同一又は似たような効果が得られることは自明である。また、本願発明には先行技術との相違を説明する具体的な実施例又は比較例がないため、同質顕著な効果の面から効果の優劣を比較することはできない。
5. 原告は更に原証2~5の実験データを提出し、本願請求項1で限定している重量比範囲が予期せぬ効果を奏し得ると主張しているが、当該実験データからは得られる効果がはっきりせず、且ついずれも相違点を検証するにあたっての既知の先行技術と比較した対照例が含まれていないため、先行技術に対して進歩性を有しているとは認定し難い。
[1] 知的財産及び商事裁判所111(2022)年行専訴字第2号判決
[2] Choi, Y.J., Yi, H.G., Kim, S.W., Cho, D.W. (2017). 3D Cell Printed Tissue Analogues: A New Platform for Theranostics. Theranostics, 7(12), 3118-3137. https://doi.org/10.7150/thno.19396.
[3] Hölzl K, Lin S, Tytgat L, Van Vlierberghe S, Gu L, Ovsianikov A. Bioink properties before, during and after 3D bioprinting. Biofabrication. 2016 Sep23;8(3):032002. doi: 10.1088/1758-5090/8/3/032002. PMID: 27658612.